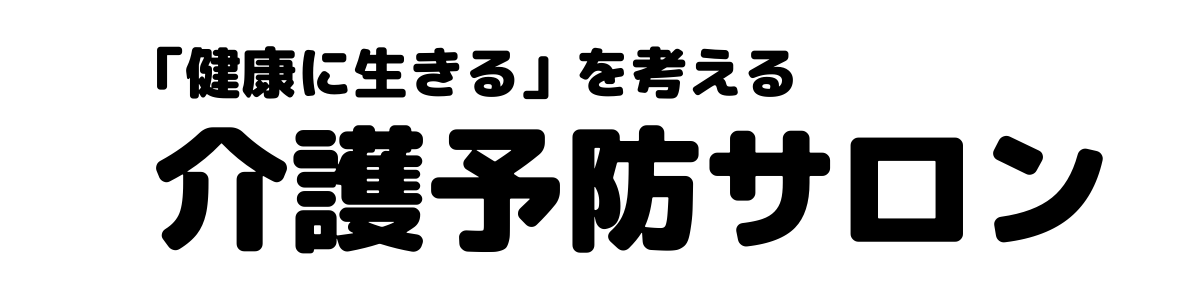自分で頑張って食事改善を行っているけど、なかなか身体に変化が現れない
食事改善は我慢が必要で辛い部分もあるので、結果が出ないと挫折してしまう原因にもなってしまいます。
食事改善で痩せない方は、食事改善のアプローチが間違っている可能性があります。
食事改善といっても、様々なアプローチ方法があり、その人の問題に合ったアプローチを行う必要があるからです。
例えば、ダイエットには、鶏の胸肉やささみが良いと聞いたからたくさん食べているという方がいたとしましょう。
確かに、たんぱく質が多い鶏肉は、ダイエットの時に良く用いられる食材です。でも、それをたくさん食べたからといって痩せれるわけではなく、逆に食べ過ぎてしまっては、カロリーオーバーで太ってしまうことも可能性もあります。
適切に食事改善を行うには、結果を左右するポイントをおさえて、今の食事を理想の食事に近づけて必要があります。
今回は、私が考える食事改善で気をつけるべきポイントをお伝えしていきたいと思います。
もくじ
太る・痩せる仕組みのおさらい
太ったり痩せたりすることを簡単に言い換えると、
太る→身体にエネルギーを溜め込んでいる状態
痩せる→身体に溜め込んだエネルギーを使っている状態 です。
基本的には、食事で入ってくるエネルギー量と身体で使うエネルギー量の関係で太る・痩せるが決まります。
なので、太るのは、食事からエネルギーを摂りすぎているか、身体で使うエネルギーが少なくなってしまっているかどちらか(もしくはそのどちらとも)といえます。
逆に、痩せるのは、食事からのエネルギーが少なくなったか、身体で使うエネルギーが増えたかのどちらか(もしくはそのどちらも)となるわけです。

仕組みとしては、意外と単純ですよね
身体で使えるエネルギーを極端に増やしたり減らしたりするのは難しいので、太る・痩せるは、基本的に食事の影響を大きく受けます。
ただ、安易に食事を抜いたり、食べなかったりすればいいのかというと、そこまで簡単な話ではありません。
確かに、食事を減らしたり、抜いたりすれば体重や体脂肪も減ります。
しかし、身体を正常に動かしたり、筋肉などの組織を作ったりするための栄養素まで抜いてしまうと、身体にとって良くない影響が起こる可能性が出てきます。
また、いつも摂っていた栄養が極端に少なくなると、身体が防衛のために栄養を使わない省エネモードになります。
そうなると、一時的には痩せますが、いわゆる停滞期に入り、痩せにくい身体になってしまうこともあります。
痩せるために食事を見直すと言っても、間違った方法では、効果が出ないばかりか逆効果の恐れもあります。
普通に食事を摂っているのが栄養の摂りすぎになっている
普通に食事を摂っているのに痩せない、でものその普通って何を基準に普通と考えていますか?
自分が普通だと思っている食事が、栄養の摂りすぎになっている可能性があります。
現代の食事は、基本的に美味しいと感じるように過剰に味付けをしている物が多いため、栄養過多になりやすい構造になっています。
例えば、ファミレスやファストフードなどの食事は、美味しいと感じるように濃い味付けが多いです。
私自身、昔は外食ばかりで、最近になって自分で食事を作るようになりました。
身体のことを考えて、薄味で食事を作っていますが、慣れるまでは正直物足りなさを感じていた時期もありました。
ただ、慣れてしまえばそれが美味しいと感じるようになり、逆に外食の味が前よりも濃く感じるようになっています。
これは、今までの習慣が出る部分なので、正直慣れの部分もありますが、慣れるまで苦労する方も多いでしょう。
アプローチ① 食事量を確認
いくら身体にいいものやダイエットに効果的なものを食べていても、量を食べ過ぎてしまっては痩せません。
ダイエットに良い食材といっても量が多くなれば、余分な栄養として身体に蓄えてしまうからです。
食べすぎかどうかを確認するために、自分にとってのベースカロリー(太りも痩せもしない摂取カロリー)を確認します。
簡易的な方法としては、除脂肪体重×40(kcal)で大体のベースカロリーが出ます(普段ほとんど運動しない方は、35でもいいようです)
例えば、体重60kgで体脂肪率20%の方だとしたら、
60-(60×20)÷100 = 48kg(除脂肪体重)
48×40 = 1920kcal(ベースカロリー)
このベースカロリーより食べ過ぎてしまっている場合は、太ってしまう食事量なので、食事量を見直す必要があるというわけです。
痩せるためには、ベースカロリーより少ないカロリーになるように、食事量を調整します。
1ヵ月で1kg落とすとしたら、1日あたりベースカロリーより大体300kcal少ないカロリーを摂取する計算になります。
もちろん、体重や体脂肪で計算しているので、変化が出てくれば都度計算しなおして、管理していかなければなりません。
今回は比較的簡単な方法として、カロリーの摂取量で食事量を管理する方法をご紹介しました。
今回ご紹介したのは、簡便にできる方法でしたが、より正確にやりたいという方は、他にもいろいろな方法もありますので、ぜひ調べてみてください。
アプローチ② 食事の内容を見直す
食事量が適正になったら、その次に栄養素など食事の内容を見直します。
ベースの食事量にあわせて身体づくりに必要な栄養素を組み込んでいくことで、身体づくりのための素材を蓄えることが出来ます。
そこで、PFCバランスを目安に身体づくりに必要な栄養素が適切に摂れているかを確認します。
P:たんぱく質
計算方法:体重の2倍程度(g)
60kgの人なら、60×2=120g
F:脂質
計算方法:総カロリーの25%程度(kcal)
総カロリー1900kcalだとしら、1900×0.25=475kcal
脂質は、1g=9kcalなので、475÷9=53g
C:炭水化物
計算方法:(総カロリー)-(たんぱく質)-(脂質)(kcal)
今まで計算したものを使うと、
1900-480-475=945kcal
945÷4=236g
※たんぱく質と炭水化物は、1g=4kcalで計算
この方の場合は、
たんぱく質:120g 脂質:53g 炭水化物:236g
を1日に摂取する必要があるということになります。
慣れるまでは、このように計算した栄養素が予定通り摂れているか、確認しながら食事を摂る必要がある。

正直、慣れるまでは結構大変
食品や料理にどれくらいの栄養素が入っているかは、アプリなどので計算できるものが出ているので、ぜひ使ってみることをオススメします。
身体づくりには食事量を見直すだけでなく、筋肉などの素材になる栄養素を適切に摂ることが非常に重要です。特にトレーニングを同時に行っている方は、栄養素が適切でないと、トレーニング結果にも影響が出てきます。
アプローチ③ 食事の食べ方を見直す
太りやすい食べ方をしていると、食事量や食事内容の効果が発揮されにくくなってしまいます。
脂肪がため込まれやすい食べ方があり、生活習慣が乱れている方は、そのような食べ方をしている場合も多いです。
今回は特に多い2つの良くない食べ方について書いていきます。
早食い・ドカ食いは太る食べ方
空腹状態の身体に一気に食事を入れてしまうと、血糖値が急激に上昇してしまうので、それを抑えるためにインスリンというホルモンが多く分泌されます。
インスリンは血糖値を下げる役割の他に、脂肪細胞や筋肉へ栄養を運ぶ役割があります。インスリンが多く分泌されるということは、脂肪の合成もどんどんと進んでしまう状態となるわけです。
また、血糖値が急激に上昇すると、インスリンの働きが過剰になり、そのあと血糖値が急降下しやすくなります。
そうなると、脳が低血糖を恐れて、糖分を補給するように指令を出すため、食べたばかりなのにまた食べたくなってしまうわけです。
忙しいとどうしても早食いやドカ食いになりがちです。まずは、自宅で食べることの多い朝食や夕食からでも、ゆっくりよく噛んで食べるように意識してみましょう。
夜の食べすぎには注意する
夜は、脂肪をため込みが促進される時間帯だと言われています。その時間帯に、脂肪になりやすい食べ物や必要以上の栄養を摂ってしまっては、脂肪のため込みを手伝ってしまうことにつながります。
また、夜は活動が少なくなる時間帯でもあるので、食べ過ぎてしまうと、消化しきれないままの食事が体内に残ってしまいます。寝ている間は、消化も進まないので、余った栄養は脂肪などに蓄積されてしまいます。
このような理由から、夜の食事量は控えめにし、朝と昼の食事に重点を置くことがよいでしょう。
仕事や家事・子育てなどで忙しい生活を送っていると、食べ方も乱れている場合も多くあります。例えば、疲れていて朝ギリギリまで寝てしまえば、急いでご飯を食べざるを得ませんよね。
まとめ
食事改善の見直すべきポイントをまとめます。
- 食事量を適正に保つ
- 食事内容を身体づくりに合ったものに変える
- 太りやすい食べ方を改善する
今回はこの3つのポイントをご紹介してきました。
いま食事改善に取り組んでいるけど、なかなか結果に結びつかないという方は、自身の食生活と照らし合わせて確認してみてください。
以上、「ダイエット中の食事改善で痩せないときの見直すべきポイント」でした。
[temp id=7]
[temp id=2]